DTF顔料白インクの実用において、「沈殿なし」という主張は虚構と考えられている。中核的な理由は、二酸化チタンの物理的特性、インクの機能要件、材料科学の法則の間に存在する調和不可能な矛盾にある――沈殿は熱力学的に自発的な傾向であり、既存の技術はそれを遅らせることしかできず、完全に排除することはできない。これは以下の4つの側面から説明できる:
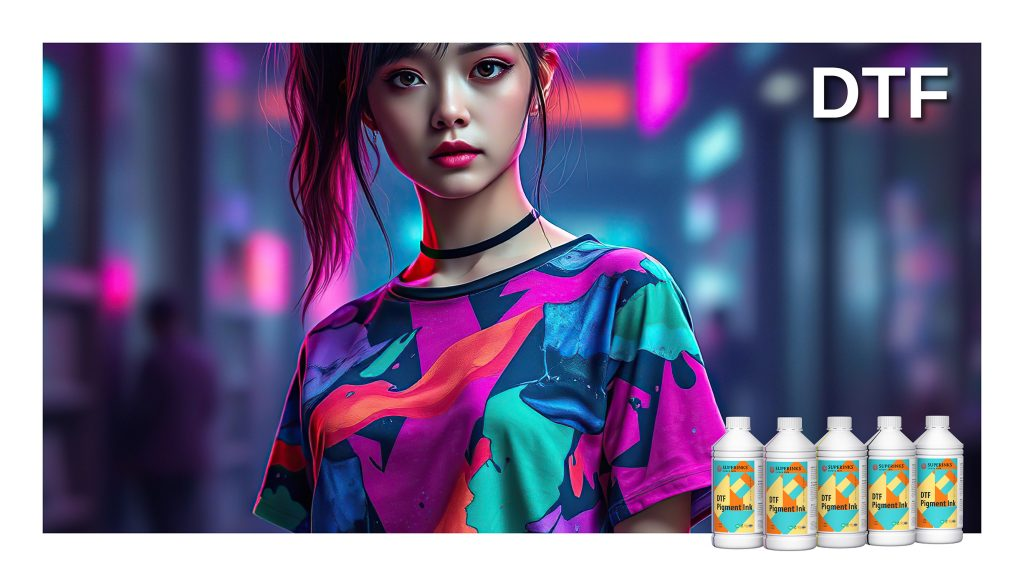
1. 二酸化チタンの物理的特性が「沈殿は自発的な傾向」であることを決定する
二酸化チタン(特にルチル型)の密度は約4.2 g/cm³であるのに対し、白インク熱転写インクの溶媒系(水、アルコールなど)の密度はわずか1–1.2 g/cm³であり、両者の密度差は3倍以上である。ストークスの沈降則によれば:
粒子の沈降速度は、粒子と溶媒の密度差に比例し、溶媒の粘度に反比例する。
これは、インク中の二酸化チタン粒子が重力により必然的に沈殿傾向を持つことを意味する。密度差が存在する限り、材料を通じてこの熱力学的に自発的な沈殿傾向を完全に相殺することは不可能である。分散剤を用いて粒子をナノスケール(例:100 nm以下)に分散させ短期的安定性を向上させたとしても、長期静置(1ヶ月以上)では「ブラウン運動の弱体化と緩やかな凝集」により粒子は徐々に沈降し、不可逆的な沈殿を引き起こす。時間の問題に過ぎない。
2. インクの「流動性」と「抗沈降性」の要件には本質的な矛盾がある
白インク熱転写インクは印刷の流暢性を満たす必要がある:ノズル孔径は通常20–50 μmであるため、インク粘度は高すぎてはならない(水系は一般的に10–30 mPa・s、油系は5–15 mPa・s);そうでないとノズル詰まりやインク不均一を引き起こす。
しかし「抗沈降性」は高粘度または強い構造的サポート(チクソトロピック系など)を要求し、高粘度は印刷流動性と直接衝突する:
沈殿防止のために粘度を大幅に上げる場合(例:50 mPa・s超)、インクはノズルから円滑に吐出できず、印刷機能を失う;
分散剤の電荷や立体障害だけに頼る場合、低粘度は維持できるが、密度差により粒子は依然として緩やかに沈降する、特に静置時は凝集を破るせん断力が欠如しているため。
この「機能要件の矛盾」は、インクが「印刷適性」と「抗沈降性」の間で妥協せざるを得ないことを決定する。印刷性能を犠牲にして絶対的な沈殿なしを追求することは不可能であり、沈殿を排除ではなく遅延させることしかできない。

3. 添加剤の役割は「遅延」であって「排除」ではなく、内在的な限界がある
既存の抗沈降材料(分散剤、懸濁剤など)のコア機能は沈殿サイクルを延長することであるが、物理法則を突破することはできない:
1. 分散剤の限定的な吸着安定性: 分散剤は物理吸着(化学吸着は稀)により二酸化チタン表面に吸着される。インク系が変化する場合(pH変動、温度上昇、溶剤揮発など)、分散剤は脱着する可能性がある。例えば:
- 低温環境では分散剤分子鎖が巻き上がり、立体障害が弱まり粒子が凝集しやすくなる;
- 長期保存後、一部の分散剤は二酸化チタン表面の不純物(鉄イオン、カルシウム・マグネシウムイオンなど)に「競争吸着」され、分散効果を失う。
2. 懸濁剤の構造的サポートは時間とともに減衰する: キサンタンガム、ファイムドシリカなどが形成するチクソトロピックネットワークは、長期静置や凍結融解の繰り返し後、水素結合や粒子間力が徐々に緩和され、ネットワーク構造の強度が低下する。結果として二酸化チタンへの「束縛力」が弱まり、最終的に沈殿につながる。
3. 高二酸化チタン含有量が不安定性を増幅する: 隠ぺい力を確保するため、白インク熱転写インクは通常20%–40%の二酸化チタンを含み、これは通常のインク(5%–15%)よりはるかに高い。高濃度粒子系では粒子間距離が短く、衝突確率が高く、凝集リスクは時間とともに指数関数的に増加する。初期分散が完璧であっても、数ヶ月後には局所的凝集と沈殿は避けられない。
4. 実用シナリオの複雑性が沈殿の必然性を加速する
白インク熱転写インクの保管、輸送、使用環境には多くの変数があり、沈殿の必然性をさらに増幅する:
- 温度変動: 夏季の高温(30°C以上)は溶剤揮発と分散剤の劣化を加速;冬季の低温(0°C以下)は懸濁剤の凍結・破乳を引き起こし、系の安定性を破壊する;
- 機械的振動: 輸送中の衝撃により、二酸化チタン粒子がせん断力で凝集し、静置後沈殿しやすくなる;
- 開放使用: 印刷時、インクは空気に曝され、溶剤揮発により二酸化チタン濃度が上昇し、凝集リスクが高まる。
実務シナリオにおけるこれらの制御不能な要因により、「絶対的な沈殿なし」は産業応用では完全に達成不可能である。実験室条件下で短期的には沈殿がなくても、実際の流通では沈殿は必然的に発生する。
結論:「沈殿なし」は材料科学の法則に反し、理想化された誤解である
白インク熱転写インクの「沈殿なし」は本質的に、熱力学と流体力学の法則に反する理想化された目標である。二酸化チタンと溶媒の密度差、インクの印刷流動性要件、添加剤の限界が共同で、沈殿が「必然的な傾向」であることを決定する。既存技術は沈殿サイクルを延長して実用ニーズ(例:1–3ヶ月以内に目立つ沈殿がなく、使用前振り混ぜで回復可能)を満たすことしかできない。
したがって、「沈殿なし」を主張する白インク熱転写インクは、長期保管の現実を無視しているか、印刷性能(使用不能な超高粘度など)を犠牲にしており、応用上問題が必ず顕在化する。